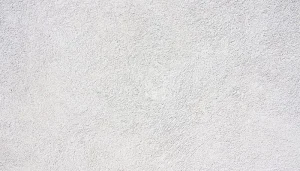事例・ケーススタディ
実際にディレクションを外注したことで成功したケースや、逆に課題が生じたケースを見てみましょう。それぞれの事例から得られる教訓を知ることで、外注活用のヒントがつかめます。
【成功事例1】小規模制作会社A社のプロジェクト納期短縮
A社はデザイナーとエンジニア数名で構成された小規模な制作会社ですが、大型クライアントのWebサイトリニューアル案件を受注しました。ところが当初、社内にディレクターがおらず、各自が手探りで進行管理をする中でプロジェクトは混乱状態に陥りました。納期は迫るのに要件変更やデザイン修正が続出し、このままでは間に合わない状況です。そこでA社は急遽、外部のベテランWebディレクターにプロジェクトマネジメントを依頼しました。外部ディレクターは着任後すぐにプロジェクトの全体像を把握し、タスクの洗い出しと優先順位付けを行いました。そして毎朝の進捗ミーティングと週次のクライアント報告をルーチン化し、チーム内の情報共有を徹底しました。さらにクライアントとの窓口を一本化して仕様変更の整理・伝達を行った結果、チームは制作作業に専念できるようになりました。その効果はてきめんで、混乱していたプロジェクトは立て直され、当初予定よりも早く納期を達成することができました。クライアントからも「進行管理が素晴らしく、安心して任せられた」と高評価を得て、A社はその後も継続案件を複数獲得する成功につながりました。この事例からは、適切な外部ディレクターの起用がプロジェクトのカギを握ることが分かります。特に自社にその役割を担える人材がいない場合、早めに外注を検討することで手遅れになる前に軌道修正できる好例と言えるでしょう。
【成功事例2】プロダクト開発企業B社のクオリティ向上
B社は新規アプリ開発プロジェクトにおいて、品質面で苦戦していました。技術者主体でプロジェクトを進めた結果、リリース直前になって不具合やUXの問題が多数発覚。社内に品質管理のノウハウが乏しく、メンバーだけでは対応が難航していました。そこでB社はソフトウェア開発に精通したフリーランスディレクターに品質管理のテコ入れを依頼しました。ディレクターは即座にテスト計画を策定し、外部のテスターも動員して総合テストを実施。さらにユーザーヒアリングを行ってUI上の問題点を洗い出し、開発チームに的確な改修指示を出しました。その結果、当初抱えていた不具合の大半をリリース前に潰すことができ、ユーザーからの評価も高いアプリを無事公開できました。B社の担当者は「外部のプロに入ってもらったおかげで、自社では気づけなかった課題に対処できた。結果的に製品クオリティが飛躍的に向上した」と振り返っています。このように専門知識を持つ外部ディレクターの力を借りることで、質の高いアウトプットを実現したケースもあります。
一方で、外注ディレクションがうまくいかなかった事例からも学びが得られます。
【失敗事例1】コミュニケーション不足による認識ズレ
ある企業C社では、デザイン制作プロジェクトのディレクションをフリーランスに委託しました。ディレクターもデザイナーも実績豊富でスキル的には問題なかったものの、定期的なコミュニケーション体制を十分に設けていなかったため、途中で齟齬が生じてしまいました。ディレクターは進捗状況を細かく報告しないまま進め、社内の担当者もディレクター任せにしてしまった結果、出来上がった成果物が当初の期待と大きくかけ離れる事態になりました。納品直前になって大量の手戻り作業が発生し、スケジュールも大幅に遅延してしまったのです。原因を振り返ると、「定期的な進捗確認や中間レビューの機会を設けなかったことにより、相互認識のズレが生じた」点が挙げられました (外部プロ人材活用のよくある失敗例!成功する導入手順と注意点完全ガイド | 株式会社Waris)。この事例の教訓は、外注したからといって完全に任せきりにするのではなく、適切な関与とコミュニケーションが必要だということです。外部ディレクターといえど、自社側との意思疎通や情報共有がなければ、本当に望む成果にはたどり着けません。定例ミーティングや進捗報告の場を設け、早期に軌道修正できる体制を作る大切さが浮き彫りになったケースです。
【失敗事例2】スキルミスマッチによるプロジェクト停滞
D社は自社初のECサイト構築プロジェクトにあたり、外部のディレクターに進行を依頼しました。しかし蓋を開けてみると、そのディレクターはWebサイト制作の経験は豊富だったものの、ECプラットフォームの知識やオンライン決済周りの専門知識に乏しい人物でした。結果として技術的な課題への対応が後手に回り、開発チームとの意思疎通もうまくいかず、プロジェクトは大幅に停滞してしまいました。これは外注ディレクターの選定時に必要なスキルセットを見誤ったことが原因です。最終的にD社は別のEC経験のあるディレクターに交代をお願いし、どうにかプロジェクトを立て直しましたが、当初のスケジュールと予算を超過してしまいました。この失敗から得られるのは、外注先選びは慎重に行う必要性です。単に実績があるからといって自社の案件にフィットするとは限りません。プロジェクトの分野や規模に合った知識・経験を持つ人材を見極めることが重要であり、契約前の面談で具体的な進め方のすり合わせや過去事例の確認を怠らないようにすべきです。
以上の事例から、ディレクション外注で成功するポイントと失敗しやすいポイントが見えてきます。成功事例に共通するのは、「自社に足りない部分を外部の力で補完した」ことと「外注ディレクターが実力を発揮できる環境を整えた」ことです。逆に失敗事例では、「コミュニケーション不足」や「人選ミス」といった要因が目立ちます。従って、外注ディレクターを迎え入れる際には、単に任せるだけでなく社内の対応体制や情報共有の場を用意し、適切な人材選びに注力することが大切だとわかります。
では、どのような企業がディレクション外注に向いているのでしょうか。基本的には「プロジェクト管理のリソースが不足している企業」や「専門的なディレクションが必要なプロジェクトを抱えている企業」が該当します。例えば、中小企業やスタートアップで専任のディレクターを置く余裕がない場合、外注を活用すれば不足リソースを補えます。また、社内にディレクションのノウハウが蓄積されていない新領域の案件(例:初めて手掛ける大型システム開発や、新規分野のコンテンツ制作など)では、経験豊富な外部ディレクターに頼る方がスムーズです。プロジェクトの繁閑が激しく、忙しい時期だけディレクターが必要な企業にも外注は向いています。一方で、常に多数のプロジェクトが走っており安定的にディレクション業務が発生する大企業であれば、内製のディレクターを育成・配置したほうが長期的には効率的かもしれません。自社の状況を見極め、外注をうまく使うことで最大の効果が得られるケースを判断することが重要です。