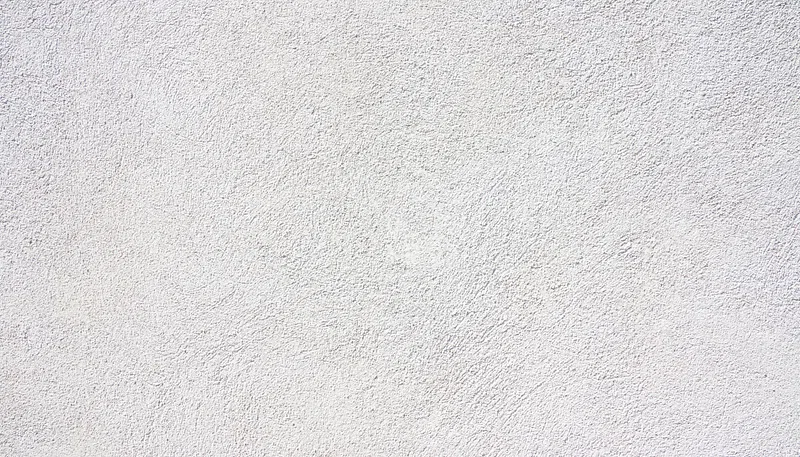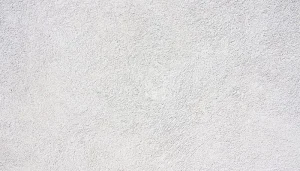目次
はじめに|なぜ修正や追加対応が止まらなくなるのか?
プロジェクトが進む中で、クライアントからの修正依頼や追加対応が止まらなくなることはよくあります。「もう少し調整したい」「やっぱりここを変えたい」「競合のサイトを見ていたら、これも入れたくなった」——こうした要望に振り回され、気づけば予定していたスケジュールもリソースも崩壊している。このような経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。
修正・追加対応が無限に発生する背景には、いくつかの共通した原因があります。
- クライアントの「完成形」が明確になっていない
- 仕様変更の影響範囲がクライアントに伝わっていない
- 修正・追加対応のルールが事前に決められていない
- クライアント側の意思決定が遅く、途中で意見が変わる
こうした状況を防ぐためには、ディレクターが適切にコントロールし、「どこまでを対応するのか」「変更が発生した場合にどうするのか」 を明確に定めておくことが必要です。
本記事では、修正や追加対応が無限に発生しないための具体的なディレクション術を解説します。
1. 無限修正・追加対応が発生する典型的なパターン
修正や追加対応が止まらなくなる状況には、いくつかの典型的なパターンがあります。
CASE
クライアントの意見が途中で変わる
プロジェクトの初期段階では「この方向でお願いします」と言っていたクライアントが、途中で競合サイトを見たり、社内で意見が変わったりすることで、「やっぱり別の形にしたい」と言い出すことがあります。この場合、プロジェクトの軸がブレ、何度も作り直しが発生するリスクが高まります。
CASE
要件が曖昧なままスタートしてしまう
「とりあえず作ってみてから考えたい」といった形でプロジェクトがスタートすると、制作側とクライアント側で完成イメージが共有されていないため、完成間近になって「これではダメだ」と大幅な修正が発生することがあります。
CASE
「試しにやってみて」からの泥沼化
クライアントが「一旦試しにこの案も作ってみてほしい」と言い出した場合、その試作案が採用される可能性が高くなり、結果的に当初のスケジュールを超えて対応しなければならないケースがあります。
2. 修正・追加対応をコントロールするための事前準備
修正や追加対応が無限に発生しないためには、プロジェクト開始前の準備が最も重要です。ディレクターがしっかりとルールを決め、クライアントと合意を取っておくことで、後々の混乱を防ぐことができます。
POINT
「修正の範囲」を明確にする
最初に「どこまでを修正対応の範囲とするのか」を明文化し、契約書や仕様書に記載しておくことが大切です。例えば、以下のようなルールを設定できます。
- デザイン修正は〇回まで無料、それ以降は追加費用が発生
- 機能の追加は「別プロジェクト」として扱い、改めて見積もりを作成
- 軽微な修正(テキスト変更・カラー調整など)と、大幅な修正の区別を明確にする
クライアントが修正を依頼する際、あらかじめ決められたルールがあることで、「無限に修正できるわけではない」ことを理解してもらいやすくなります。
POINT
仕様変更が発生した場合のルールを決める
プロジェクトの途中で仕様変更が発生するのは避けられません。しかし、その影響をコントロールするために、以下のようなルールを決めておくことが有効です。
- 変更が発生した場合は、影響範囲を明確にし、納期やコストの調整を行う
- 「この変更を加えるなら、何かを削る必要がある」などのトレードオフを提示する
- 仕様変更はクライアントの正式な承認を得た上で対応する
このルールを徹底することで、クライアントが「簡単に変更できる」と思い込むことを防ぎ、慎重に意思決定をするようになります。
3. 修正依頼を受けた際の対応フロー
事前のルール設定をしていても、修正依頼がゼロになることはありません。修正が発生した際に、どのように対応すればスムーズに進められるのかを見ていきます。
STEP
クライアントの要望を整理する
修正依頼が来たら、まずその要望の意図を明確にすることが重要です。
- クライアントが求めているものは何か?
- その修正は本当に必要か?(目的と合致しているか?)
- どの程度の影響があるのか?
特に「なんとなく違う」という抽象的な要望に対しては、「どの点が違うと感じるのか?」を掘り下げ、具体的なフィードバックに落とし込むことが重要です。
STEP
変更の影響を伝え、クライアントと合意を取る
修正や追加対応には、必ずコストや納期への影響があります。変更を受け入れる場合、その影響をクライアントに適切に伝え、合意を取ることが必要です。
- 「この修正には〇日追加の工数が発生し、納期が△日延びます」
- 「無料で対応できる範囲はここまでです。それ以上は追加費用が発生します」
- 「この修正を行うと、他の機能との整合性に影響が出るため、慎重に検討したいです」
このように、変更のメリット・デメリットをクライアントと共有し、意思決定を促すことで、不要な修正を減らすことができます。
4. 修正・追加対応をコントロールするディレクションの技術
ディレクターの役割は、クライアントの要望と制作側の負担を適切に調整することです。そのために、次のようなテクニックを活用するとよいでしょう。
テクニック1:修正依頼を「代替案」に変える
「ここをもっと目立たせてほしい」と言われた場合、「文字を大きくする」という方法だけが解決策ではありません。「色を変える」「配置を調整する」といった代替案を提案することで、クライアントの要望を満たしつつ、制作側の負担を減らすことができます。
テクニック2:修正対応の締め切りを設ける
クライアントが「あとでまた考えたい」と先延ばしにしてしまうと、修正依頼が際限なく増えてしまいます。「修正対応は〇日までにまとめて提出してください」と締め切りを設定し、都度対応を防ぐ工夫が必要です。
まとめ
修正や追加対応が無限に発生しないためには、プロジェクトの初期段階でルールを決め、クライアントの意思決定を適切にコントロールすることが重要です。
- 修正の回数・範囲を事前に合意し、ルール化する
- 仕様変更の影響を明確にし、納期やコスト調整を行う
- 修正依頼を受けた際は、要望を整理し、代替案を提案する
- 締め切りを設け、修正依頼が際限なく増えるのを防ぐ
適切なディレクションが行われれば、制作側の負担が減り、クライアントも納得感を持ってプロジェクトを進めることができます。無駄な修正を防ぎ、効率的にプロジェクトを完了させるために、ディレクションの技術を活用しましょう。